ある日突然くる「親の入院・通院」
「お母さんが倒れて、救急搬送された」
そんな一本の電話で、日常は一変します。
着の身着のまま病院へ駆けつけ、医師の説明を受けても、頭が真っ白。
「何を持ってくればいいの?」「これからどうなるの?」
そんな不安や戸惑いを、多くの方が経験します。
私は医療ソーシャルワーカーとして、数えきれないほどの“突然の入院”の現場に立ち会ってきました。
そこで痛感するのは、事前に少し準備しておくだけで、家族の混乱は大きく減らせるということです。
今回は、親の入院・通院で慌てないための「5つの準備と心構え」をまとめました。
準備1:基本書類の把握と保管
入院時に必ず必要になるのが、以下の書類です。
- 健康保険証(マイナンバーカード、資格確認書)
- お薬手帳
- 診察券(かかりつけ医・通院先)
- 介護保険証(該当する場合)
これらがバラバラの場所にあると、探すだけで大騒ぎになります。
100円ショップのファスナー付きケースや、書類整理ポーチにひとまとめにしておきましょう。
さらに、スマホで写真を撮っておくと、万一紛失した時の確認にも役立ちます。
家族LINEグループで共有しておくのもおすすめです。
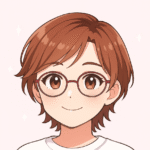
マイナ保険証に関しては、以下の記事も参考になります。
https://akari-note.com/マイナ保険証への切り替えと資格確認書/
準備2:「医療情報の共有ノート」を作ろう
救急搬送時や初診時、医療者に必ず聞かれるのが次のような項目です。
- 持病(心臓病・糖尿病など)
- 飲んでいる薬(処方薬・サプリも含む)
- アレルギーの有無
- 手術歴
- かかりつけ医や主治医の名前
これらをその場でスラスラ答えられる家族は、意外と少ないもの。
そこで活躍するのが「医療情報ノート」です。
ノートやスマホメモにまとめておくだけで、救急搬送や入院時の説明がスムーズになります。
私は患者さんご家族に、「書き方がわからない場合は、この項目だけでもメモしてください」とお渡しすることもあります。
準備3:「支払い・手続き」などお金と制度の基本知識
入院が長引くと、医療費や生活費の負担が心配になります。
そんなとき役立つのが、次の制度です。
- 高額療養費制度(自己負担額を一定額までに抑えられる)
- 限度額適用認定証(入院前に取得すれば、窓口での支払いが軽減)
- 介護保険のサービス(入院に限らず早めに利用できます)
また、親の通帳や印鑑の保管場所、キャッシュカードの暗証番号を共有しておくと、支払いの際に慌てません。
心構え1:「感情が揺れるのは自然」―まずは深呼吸を
親の病気や入院は、心に大きな負担を与えます。
突然の出来事に、驚きや不安、怒り、無力感…。
その感情は自然なものです。
私も、ご家族が医師への苛立ちを見せる場面を何度も見てきました。
それは「説明がわからない不安」や「状況を把握できない戸惑い」が背景にあることが多いのです。
まずは深呼吸をして、感情を落ち着けましょう。
そして、「聞いてもいい」「確認していい」という気持ちを持つことが大切です。
※医師の説明がわからないときの対処法についてはこちらの記事もおすすめ!
心構え2:ひとりで抱え込まない「受援力」を持つ
すべてを自分だけで背負う必要はありません。
兄弟姉妹や親戚、友人、そして地域の支援制度を頼っていいのです。
- 地域包括支援センター
- 病院の医療ソーシャルワーカー
- ケアマネジャー
頼ることは弱さではなく、家族を守るための大切な力です。
私自身、数多くの現場で「早く相談してくれてよかった」と思う瞬間を見てきました。
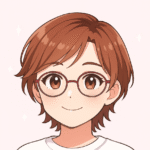
50代になると、心を許せる相談相手に迷うこともありますよね。
頼る力「受援力」についてはこちらの記事もおすすめ!
50代、孤独を感じたときに大切にしたい“受援力”という考え方
おわりに:いざという時の「安心」は、日々の小さな備えから
入院や通院は、いつか必ず訪れるかもしれない出来事です。
そのとき、今回ご紹介した「5つの準備と心構え」を少しずつ整えておくだけで、あなたと家族の負担はぐっと軽くなります。
大切なのは「今から少しずつ」。
今日できることから始めて、安心を積み重ねていきましょう。
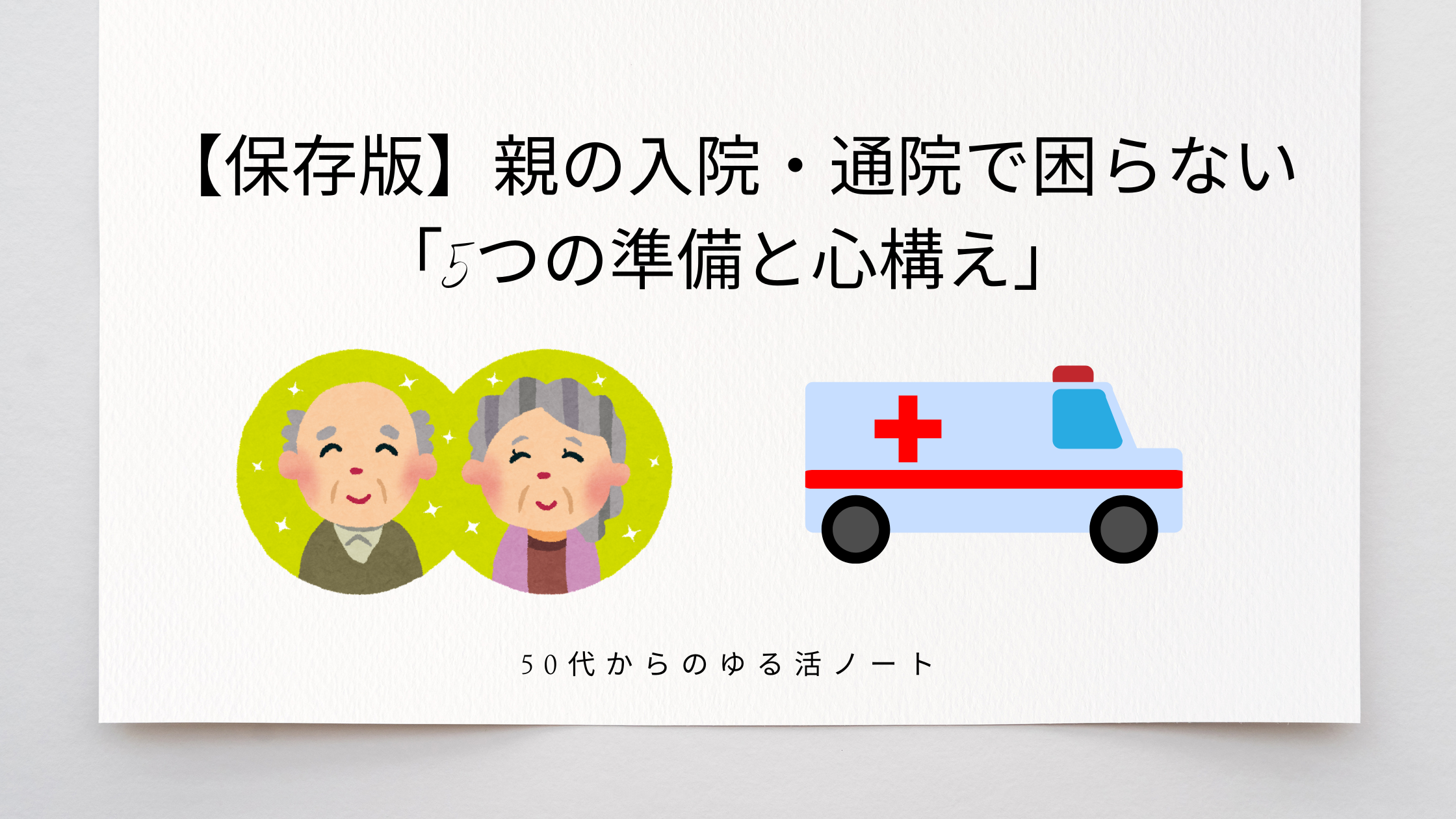
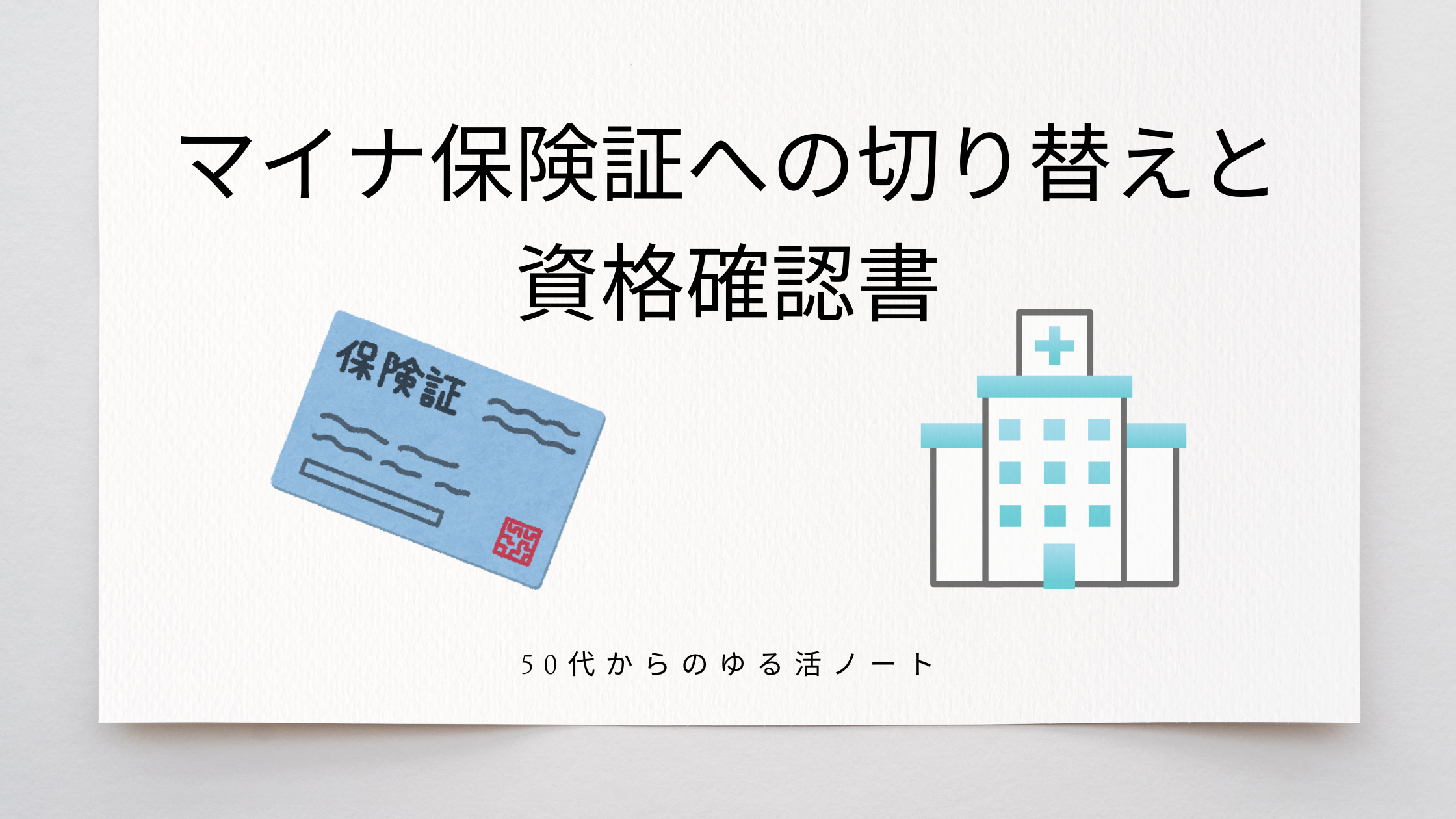
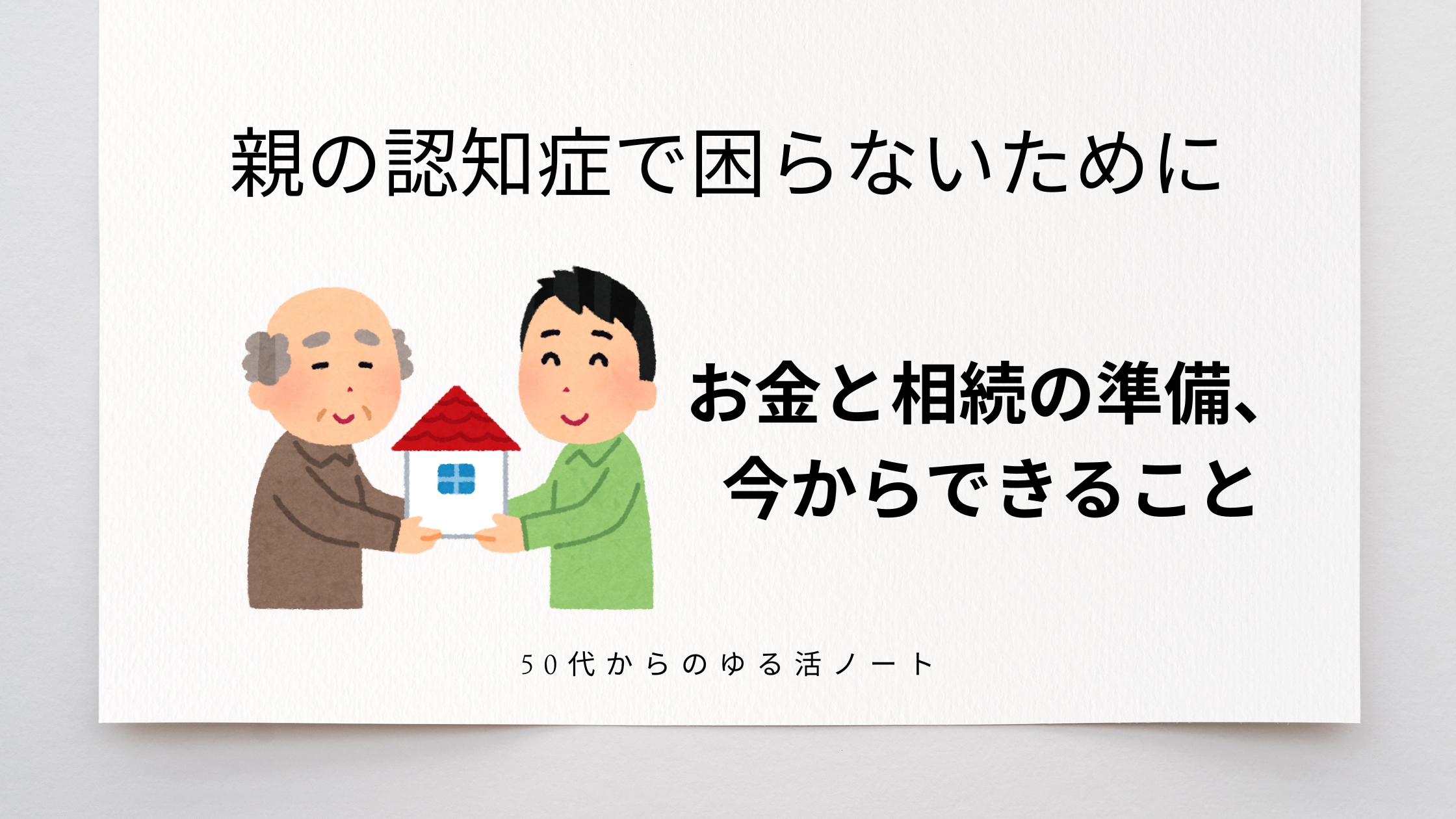
コメント