実家のアパートを見上げるたびに、胸の奥でちくりとした思いがよぎります。
「空き部屋のまま置いておくのは、もったいないな…」
築年数が経っていて、賃貸として貸すにはメンテナンス費用や維持費がかかる。安く貸してしまえば、いざ家族で使いたいときに自由に使えない。
父は認知症が進みつつあり、妹と一緒に暮らしを支える中で、これからの生活や相続について考える場面も増えてきました。
相続不動産を、ただ「残す」だけではなく、「どう活かすか」。その視点が、私の中で少しずつ大きくなっていったのです。
民泊という選択肢との出会い
不動産活用について調べる中で出会ったのが「民泊」でした。
最初は「地方に海外の旅行者なんて、本当に来るの?」と半信半疑。けれど、情報を集めていくうちに「交流」というキーワードに惹かれました。
ただ部屋を貸すだけではなく、人と人が出会い、地域や暮らしを共有できる仕組み。
「これなら、築古アパートに新しい命を吹き込めるかもしれない」
そう思った瞬間、少しワクワクする自分がいました。
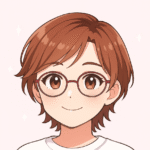
ぽんこつ鳩子さんの「民泊1年生の教科書」を即購入。
YouTubeやブログなどで情報を得て、chatGPTの力も借りながら民泊開設までのステップを調べまくりました👍
医療ソーシャルワーカーとしての私と重なる部分
私は病院で医療ソーシャルワーカーとして働いています。
患者さんやご家族の話を聴き、生活を支える仕組みを一緒に考える仕事。
そこにあるのは「人とのつながりを大切にすること」でした。
だからこそ、民泊の「交流」という価値に、自然と共感したのかもしれません。
定年後も自分らしく働きたい。人と関わり、地域とつながり続けたい。
民泊は、そんな私のこれからの生き方に寄り添う選択肢の一つに見えたのです。
家族にとっても、地域にとっても
もちろん、現実的な課題はたくさんあります。
父に説明すれば混乱するだろうし、妹にも負担がかかるかもしれない。
でも、民泊はただの収益事業ではなく、家族の安心や地域の交流にもつながる可能性があります。
父が過ごしてきた家を、これからも人が集える場所にする。
妹と協力しながら不動産を活かす。
そして、自分自身の未来の働き方を準備していく。
「民泊を始めたい」と思った背景には、そんな複数の想いが重なっています。
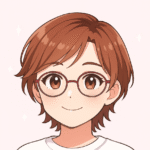
現実は厳しい😣
父に空アパートを私に貸してほしいと伝えた翌日、いろいろ考えたのか、
「勝手なことをして、儲けて独り占めしようとしている」
「不動産屋に任せているのに、不動産業をするつもりなのか?」
妹に、なんでアパートが空いていると教えたんだと怒っていたそうです😥
混乱させてしまったと反省。でも少しずつ理解してもらうようにしたいと思っています。
小さな挑戦から始める
大きな一歩を踏み出すのは怖い。けれど、小さな一歩なら踏み出せる。
実家のアパートを舞台にした民泊は、まさにその一歩です。
いつかは相続する資産。だからこそ、今のうちに「活かす方法」を探りたい。
父や妹との関係を大切にしながら、地域の中で人が集える場所をつくりたい。
そんな思いを胸に、私は今日も一歩ずつ、準備を進めています。
それはきっと、私自身の「これから」を形にする挑戦でもあるのです。
もちろん、民泊は「やりたい」と思っただけでは始められません。
実際にはどんな準備が必要なのか?どんな壁にぶつかるのか?
次回は、私が民泊を始めるために最初に動いたことについて書いてみます。
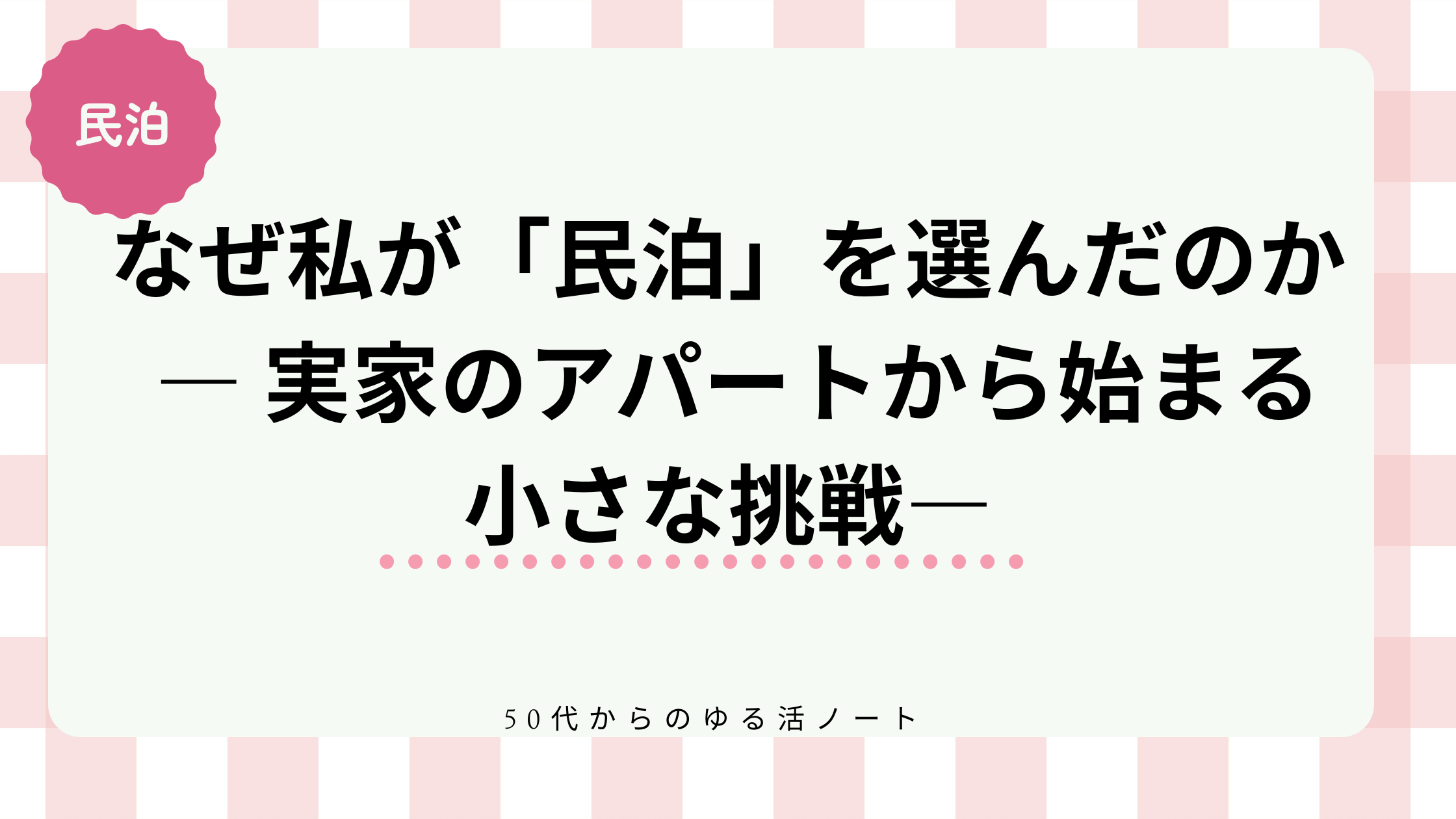
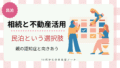

コメント